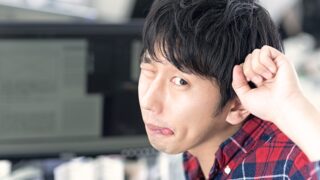自分のサイト記事を検索していたら、ものの見事に記事がパクられていたことを発見しました。
5記事がイラストや画像もまるまる完全コピーされていました。
そこで「サイト記事がパクられたサイトへの対処法」についていろいろ調べてみました。
その対策としては5点あります。
1.記事をFetch as Google(フェッチアズグーグル)を使って即効でインデックスさせる
2.Googleの検索エンジンに素早くインデックスさせれるWordPressプラグインPubSubHubbubを導入する
3.コピーされたサイト運営者に連絡し厳重注意
お問い合わせがあるのでそこから連絡し、重複コンテンツが無駄だということを伝える
例えば、次のような文面でコメントを残す、直接メールを送ってみましょう。
(メール文例)
—————————————-
「私は○○のサイトを運営している○○(HNで可)と申します。
以下URLで掲載しているあなたのブログ記事は事前の確認もなく
無断で使用されています。
複数の記事において著作権を、侵害している可能性がありますので、
即刻削除要請を致します。
あなたのブログURL
当方のブログのURL
あなたも、コピーして部分のコンテンツとして利用することは
効果がないばかりか、法に抵触することはご存知でしょう。
この件に関する明確は理由の返事がなかったり、記事の削除をされない場合は、
法的処置を取らせていただきます。」
—————————————-
4.極め付けはこれです
グーグルへ著作権侵害による削除要請
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&hl=ja
5.コピペ防止するためのプラグインを導入して、
まるパクリのハードルを高めて、あきらめさせる、
ただ、このような規約違反ブログのパクリを完全に防ぐことは、今のところ不可能です。
私もこのような経験があり、一応Googleに連絡しましたがその対応は様々です。
証拠がないので対処できないというケースや相手側のサーバーにも連絡しましたが、結局は対処してもらえなかったりしました。
パクられたほうが順位を下げるのは理不尽ですが、Googleの技術もまだ行き届いていないようで、対応を見守るしかないみたいです。
一応「右クリック禁止」のタグを埋め込んでコピーしにくくしてありますが、これも完全とはいえません。
パクろうと思えば、いくらでもできてしまいます。
以下のコピー防止策を講じる方法です。
■「右クリック禁止」タグの使い方
「右クリック禁止」タグの使い方にも注意することがあります。
今後は、資産価値があるサイトは、著作権の問題もあるので、このような対策も考えておく必要があるかもしれません。
昨日も話しましたが、SEOにしても、コピペ対策にしても、イタチごっこの繰り返しです。
不動な価値は、「役に立っているか」「ユーザーのためになるか」です。
要するに、アフィリエイトサイトも「社会貢献度」で評価されているのです。
あとは、コピペ防止するためのプラグインを導入して、まるパクリのハードルを高めて、
あきらめさせる、という手がありますね。
■HTMLサイトの場合
bodyタグを下記のように書き替えます。
‘コピー禁止’の部分を自分の好きな文章に変えてください。
コピーしようとすると警告文が表示されます。
「コピーは犯罪です!」
「右クリックはできません。」
など、注意文を書けばいいです。
「警告文なし」なら、
bodyタグを下記のように書き替えます。
WPブログの場合
不正コピー防止できるプラグインがあります。
コピペを防止する為に「右クリック禁止」の警告文が出ます。
http://wordpress.org/plugins/wp-copyright-protection/
メインブログはこのプラグインを入れています。
他にも、「コピペ防止タグ」や「コピペ禁止タグ」で
検索するといろいろ出てきますよ。
ただ、ユーザーにとっては、コピペ目的とは限らないので
「右クリックできないことが不便」と感じる場合があります。
何かを参考にするためにコピペして検索したり、URLを貼るなど、
ユーザーが再利用したい場合は、禁止タグを使わないほうが優しいサイトになります。
コピペ禁止タグも、ユーザーにとっては面倒、じゃまになるケースもありますから、よく考えて使いましょう。
最優先することは、「ユーザーの動向」「ユーザーの問題解決」です。
ユーザーのニーズや要求があって、コンテンツが成り立ちます。
サイト作成で迷ったら、まずこれを考えましょう。
そのために、サイトを更新して改善していきましょう。
なので、目的によって使い分けるのがいいですね。